| ページ數 | 行數 | 問題の箇所 | 説明 |
|---|
| 20 | 後ろから一行目 | 甚七の子の鐵 | 田中鐵治郎。曾和佐次右衞門の妹「もゝへ」の夫。 |
| 25 | 一行目 | 猫憑き | お婆様の名は「いち」。實際に死んだのは、田中家が夏見へ移轉して後。鐵をぢが猫を捨てに行つたのは、三本松とのこと。 |
| 27 | 後ろから四行目 | 河合又五郎 | 寛永十一年、平成前三百五十五年、鍵屋の辻で渡邊數馬と荒木又右衞門に討たれた。その前夜は島个原に泊つたので「本陣宿に泊つた」と想像してゐる。又五郎の墓 は、上野市寺町の萬福寺にある。(冩眞を押すと大きい冩眞が見られます。) は、上野市寺町の萬福寺にある。(冩眞を押すと大きい冩眞が見られます。) |
| 32 | 後ろから四行 | 三行り半 | 江戸時代に離婚に際し、妻が夫に書かせた離婚證明書。再婚の自由を證明したもので、本文を三行半にかいた。東川なつは明治十二年うまれで、明治四十四年に佐那具の服部泰輔と結婚してゐるので、離婚に三行り半は辻褄が合はない。しかし、三下り半の習慣は明治にも殘つてゐたと考へると、全くの創り話でもないかも知れない。 |
| 41 | 後から七行目 | 小學校は | 箕曲村夏見は箕曲小學校の通學區で、東川の本籍地である名張町松崎町は名張小學校の通學區。夏見の坊垣からは距離的には同じ位。
箕曲小學校は松永屋敷(松永誠也の實家)跡に、名張小學校は藤堂家名張陣屋跡に、それぞれある。
松永は藤堂家の家臣。
|
| 41 | 後から六行目 | 勇三の父 | 勇三は東川とみの妹「すゑ」の子。いし松は、すゑの夫「誠也」の通稱名。當時、名賀郡役所に勤務。 |
| 44 | 後から六行目 | 曾爾街道 | 名張から奈良縣宇陀郡曾爾へ通じる曾爾街道建設に當り、曾和の分家の曾和喜代太が最初に盡力した。その縁で佐次右衞門が私費で記念碑建設を目論んだ。記念碑は現在、夏見の積田神社前にある。(平成十四年正月現在、道路擴幅工事で片付けられてゐる。)曾爾街道については、『伊賀國 - いがのくにふるさとはなし』の中の「伊賀國曾和家」も参照されたい。 |
| 47 | 前から五行目 | ヌケソ | 淨瑠璃の『伊賀越道中雙六』の「鶴が岡の段」に、和田志津馬が見えなくなつた澤井股五郎を探して「股主々々どれへござつた。ぬけそとは手が惡い。人をころりと殺して置て、迯ふとは卑怯者」とあり、欄外の註に「ぬけそ─逃げる」とある。(塚本哲三編輯『海音半二出雲宗輔傑作集 全』大正七年、有朋堂書店、有朋堂文庫傑作集、第四八二ページ) |
| 47 | 後から二行目 | 客馬車 | 名張・上野間の乗り合ひ馬車。鐵道が行き渡る前には全國に驛馬車が普及した。 |
| 48 | 一行目 | 手首の無い | 定吉の實母「小さ以」は、帽子工場で働いてゐた時の事故で左手首を失つた。 |
| 49 | 七行目 | 前田、または後出 | 夏見の坊垣小場のうち、高臺一帯は「カミヤシキ」、そのすぐ下は「マヘダ」、川沿ひは「ヘヤノカハラ」といふ。坊垣に續く高臺は「ウシロデ」といふ。 |
| 51 | 一行目 | 譲 | 夏見の積田神社の裏から下比奈知へ抜けたすぐの小場。 |
| 51 | 三行目 | 香落 | 曾爾街道の途中にある奇岩景勝の渓谷。 |
| 51 | 三行目 | 坊垣の地蔵 | 當時、定吉が住んでゐた家から表通りへ出た所にあつた石佛。現在の位置 は道路擴幅工事により、少し後ろへ引いて、下流へ移動してゐる。(冩眞を押すと大きい冩眞が見られます。) は道路擴幅工事により、少し後ろへ引いて、下流へ移動してゐる。(冩眞を押すと大きい冩眞が見られます。) |
| 60 | 七行目 | 蓮華の仕事 | 蓮の葉の上に乘つた形の墓石。 |
| 63 | 後から一行目 | うたのをば | 「うたの」は佐次右衞門のすぐ下の妹。紀州粉河の宮本米太郎の妻。 |
| 67 | 六行目 | 松本宗やん | 極めて腕の立つた指物師。定吉の親友。第五十九ページの冩眞の向かつて左端。 |
| 75 | 六行目 | 川崎さん | 川崎克。上野出身の代議士。川崎二郎の先々代。元來、天守閣の無かつた上野城跡に、産業振興のために天守閣に模した建物を建設した。 |
| 77 | 後から八行目 | 赤紙 | 兵役の召集令状は薄赤色の紙に印刷されてゐたので「赤紙」と言はれた。 |
| 77 | 後から七行目 | 笑ひながら | 『留書』には、「戰爭に行くのは厭だ」と泣いた人があつた、と書かれてゐる。 |
| 93 | 一行目 | 荒塵 | 鐵道兵の歌。『天翔艦隊』といふ優れたページを發表してゐる『天翔艦隊』の司令長官、天翔さんに敎へて戴いたところによると、「これは比較的有名な軍歌で、藤田まさと作詞、大村能章作曲の「黄塵」」とのこと。 |
| 98 | 一行目 | 楊維盛氏から貰ふた詩 | 今は表装して額に入れてある。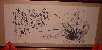 (冩眞を押すと大きい冩眞が見られます。)文面は「一國/蘭草亂/如蓬葉/焼花甜/氣候濃迎/風送春/非不遠□能/送到俗塵中/民國廿七年 爲/東川先生大人順正/法学士楊維盛」と讀める。 (冩眞を押すと大きい冩眞が見られます。)文面は「一國/蘭草亂/如蓬葉/焼花甜/氣候濃迎/風送春/非不遠□能/送到俗塵中/民國廿七年 爲/東川先生大人順正/法学士楊維盛」と讀める。
このほかに、別の人から貰つた「中日友好」と書いた書もある。 |
| 113 | 十一行目 | 外科手術 | 定吉の話では、後日、その手術の後がどうなつたか尋ねたところ、傷跡を消毒しに、通つてゐると言つてゐたとのこと。 |
| 115 | 三行目 | 進め機關車よ | 鐵道兵の歌で、『天翔艦隊』の「軍樂隊」に歌詞と曲が紹介されてゐる。 |
| 147 | 五行目 | 北谷 | 名張の電機屋。東川とみの母方の親戚。 |
| 149 | 二行目 | 松永春 | 春子。東川とみの甥「勇三」の妻。 |
| 152 | 一行目 | 徴用 | 戰時下の國民総動員で政府指定の軍需工場へ職場指定された。定吉は鍛造工として海軍工廠へ徴用されたので、千葉鐵一では鍛造工としての職業訓練を受けた事が判る。千葉鐵一では、鐵道運轉と鍛造に分けて職業訓練を行ふたといふ。國民総動員での「徴用」は後に、當時日本國であつた朝鮮や臺灣にも適用されたので、これを「強制連行」と表現する人がゐるが、作爲的で不適切な表現である。 |
| 154 | 後から三行目 | もゝのをば | 佐次右衞門の妹「もゝへ」。上長瀬は佐次右衞門の母の實家、羽後(はのち)のこと。 |
| 158 | 二行目 | 現役、補充 | 國民皆兵制度での兵役區分。陸軍では滿二十歳で兵隊檢査を受けて合格すると、二年間、現役兵として徴集される。現役兵員を超えた兵役適格者は補充兵に區分される。 |
| 159 | 一行目 | 後からだから知らぬ | 隊列の後から上級の者が追ひ抜いた時は、隊の後の者が聲を掛けて隊長に促して敬禮をするが、定吉は部下が促さなかつた事をとがめずに、少尉に「知らぬ」と言ひ張つた。 |
| 185 | 後から八行目 | 引退祝ひの石碑 | 大和郡山の北柳生の墓地に「鳴瀧源藏」の石碑 がある。また「三笠山」の自然石の碑 がある。また「三笠山」の自然石の碑 が名張市元町の宗泰寺にあつたが、現在は行方不明。現在、宗泰寺にある「三笠山」の石碑 が名張市元町の宗泰寺にあつたが、現在は行方不明。現在、宗泰寺にある「三笠山」の石碑 は別人の物。 は別人の物。 |
| 204 | 三行目 | 奈良監獄 | 奈良監獄と同時期に同じ設計者により建設された千葉監獄で「脱獄實驗」が行はれたことが、奈良監獄設計者、山下啓次郎の傳記に紹介されてゐる。山下洋輔著『ドバラダ門』(平成五年、新潮文庫、第百三十八乃至百三十九ページ。)奈良監獄の建物は現在の奈良少年刑務所で、明治三十六年、竣工。奈良市般若寺町十八にあり、明治煉瓦建築の代表として知られてゐる。 |
| 206 | 一行目 | 領主が違ふ | 明治以前の伊賀は総て藤堂藩領であつたが、名張町域は藤堂宮内家の支配下にあり、國津は上野の藤堂家の支配下にあつた。 |
 は、上野市寺町の萬福寺にある。(冩眞を押すと大きい冩眞が見られます。)
は、上野市寺町の萬福寺にある。(冩眞を押すと大きい冩眞が見られます。) は道路擴幅工事により、少し後ろへ引いて、下流へ移動してゐる。(冩眞を押すと大きい冩眞が見られます。)
は道路擴幅工事により、少し後ろへ引いて、下流へ移動してゐる。(冩眞を押すと大きい冩眞が見られます。)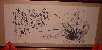 (冩眞を押すと大きい冩眞が見られます。)文面は「一國/蘭草亂/如蓬葉/焼花甜/氣候濃迎/風送春/非不遠□能/送到俗塵中/民國廿七年 爲/東川先生大人順正/法学士楊維盛」と讀める。
(冩眞を押すと大きい冩眞が見られます。)文面は「一國/蘭草亂/如蓬葉/焼花甜/氣候濃迎/風送春/非不遠□能/送到俗塵中/民國廿七年 爲/東川先生大人順正/法学士楊維盛」と讀める。 がある。また「三笠山」の自然石の碑
がある。また「三笠山」の自然石の碑 が名張市元町の宗泰寺にあつたが、現在は行方不明。現在、宗泰寺にある「三笠山」の石碑
が名張市元町の宗泰寺にあつたが、現在は行方不明。現在、宗泰寺にある「三笠山」の石碑 は別人の物。
は別人の物。